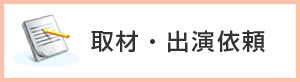火鍋
ガツンと来るものが、食べたかった。
後にして思えば、これは不適当な感想だったかもしれない。しかし、将棋が不調で外も暑すぎるほどに暑いというストレスフルな環境下、その捌け口は当然ながら食に見いだされることとなる。
ストレスを軽減するためには辛い食事が効くとされる。大阪で辛い食事として最も好まれているのはスパイスカレーだろう。大阪は人口当たりのカレー屋が日本一と言われるほどのカレー帝国で、夜は別のお店をやっているところが昼だけランチカレーを出しているようないわゆる「ヤドカリカレー」(宿を借りてカレーを作るのでこのような名称になっていると思われる)と言われるカレー屋も数多くある。なおかつクオリティ、コスパともに上々である。
また、関西将棋会館という場所からすれば、その対抗馬に上がる「辛旨」な食事は麻婆豆腐だろう。福島にはランチ時に行列が出来る麻婆豆腐の店が多く、棋士も昼食の際に好んで食べるものが多い。研究会などのランチに麻婆豆腐を頂くと、爽快な辛味が午後からの活力と夜型が多い棋士にとっては少し寝ている脳味噌に心地の良いパンチを与えてくれるのだ。
大抵の棋士にとっては辛い食事と言えばこの二つが挙げられるだろう。
しかし、広島人(主語が大きすぎるのではないでしょうか※管理人注)はより辛いものを好む。「つけめん」と言えば広島以外の地域では麺とスープが別個となったラーメン様の麺料理を指すが、広島で「つけめん」と言えばそれはすなわち唐辛子やラー油の入った激辛つけだれをベースとしたものを指す。また、「キング軒」など辛さを調整できる汁なし担々麺を出す店もその勢力を伸長し続けている。カレーや麻婆豆腐はそれらを上回る辛味力を持つとは言えないだろう。もっとガツンと来るものが必要だった。
「そうだ、火鍋を食べに行こう」
VS(二人で行う研究会)を終えた私は、相手をしてくれた奨励会員にそう提案した。丁度彼(仮にN君としよう)も不調期で、何かを吹き飛ばさなければならないところだと思っていたのか、快く快諾してくれたのだ。N君は未知の食事に対する好奇心が強く、関西棋界ではそのアグレッシブさで知られている。おそらく初めてとなる火鍋も彼なら食べたがるだろう、と思ったのだがその読みは当たっていた。
さて、本来中国ではほとんどの鍋料理を「火鍋」と表現するらしいが、日本で「火鍋」といえば大抵四川風の唐辛子が沢山入った鍋を指すだろう。そして、折角体験するなら本場の「火鍋」を体験してみたい。私達は難波の一角にある四川風火鍋の店に当たりをつけ、そこに伺ってみることとした。
その店は、まさに「本場」という雰囲気だった。店内も中国式の文様に彩られ、案内も中国語の表記が多く、QRコードでの注文システムもほぼ中国語だった。漢字であれば読めるのではないか、という淡い期待は簡体字の(簡略化された漢字)の前に打ち砕かれた。中国語の勉強は麻雀と中国哲学の授業を一部取っていたくらいしか覚えの無い私は、泡沫の期待を抱いてN君に目配せするものの、残念ながら彼も全くの無縁のようだった。
しかしこれも食の勉強、と私達は燃え上がる。とりあえずメインの鍋は雰囲気で分かったので、ベースの火鍋を一つ注文し、初めはお試しとばかりに「普通」の辛さを注文する。
そしてアルコールや前菜も頼んだのだが、この時一つ悲劇が起きた。せっかくなので二人とも現地のお酒を注文しようとしたのだが、N氏が注文したものがなんといわゆる白酒、スピリタスの部類だったのだ。銘柄名での表記であったためメニュー名からは見抜けなかったのである。おそらく本場では聞けばわかる程度には有名なお酒だったのだろう。
前菜が到着して、早速味見にかかる。火鍋は当然辛いだろうから、安牌を中心に頼んだつもりだったのだが、青菜の炒め物も中々に辛い。やはり火鍋専門店ならでは、唐辛子はふんだんに使われているようで、注文の中で辛くないものは豚肉のから揚げくらいのものだった。白酒と辛い炒め物の挟み撃ちに合い、しまいに青唐辛子をそのままつまんでしまったN氏からすぐに豚肉のから揚げのお代わりの声がかかる。
さて、こうしてつまみを色々食べるのも楽しいのだが、火鍋の到着前にタレを作らなければならない。火鍋はタレの種類の豊富さも魅力で、この店では取り放題の様々な調味料や薬味を使ってタレを作ることとなる。オーソドックスなゴマだれやポン酢から、パクチーやごま油まで、色々な味が楽しめるのは嬉しい。N君がオーソドックスなタレを作る中、わたしはオイスターソースを手にして広島出身を主張する。
タレが数点作られ豚肉のから揚げに再びお代わりの声がかかるころ、ついに本命の火鍋が到着する。こちらの火鍋は縁起物らしく、鍋に開運の祈りの紙が掛かっており、到着の際におそらく(残念ながら私達は中国語を音声では解さなかった)開運祝いの声を合唱してくれる。その後、鍋にスープが注ぎ込まれ、唐辛子が鍋の底からビジュアル的にも沸き立ち、スープが赤く染まる。日本に多い中央に仕切りがあって真っ赤なスープと白湯の二色鍋ではなく、ただただ赤い鍋である。見た目には非常に綺麗な光景だが、ここからがいよいよ本番の始まりである。
今回挑戦した火鍋の特徴として、鴨血(ヤーシェ)と言われる食材が入っている。アヒル(家鴨)の血が豆腐のような形に造成されており、ぷるんとでも言おうか、非常に面白い食感がする食べ物である。他にも多種多様な食材を注文することが出来るのだが、色々な動物の肉や部位も指定することが出来るあたり(おそらく100種類は超える追加注文が出来る)、流石本場の店である。私はラム肉が気に入り、N君は新しい味に挑戦するために少しずつ肉や部位の注文を変えて試していた。
この時は気付かなかったのだが、私達は大きな過ちを犯していた。そう、鍋の取り皿に唐辛子を入れっぱなしにしていたのである。これをそのままにしていると、どんどん辛さが増してくる。唐辛子は毎度取り除かなければならないのである。そして追加注文の白菜が曲者だった。白菜は非常に良く汁を吸うため、ただでさえ濃縮された辛味が口の中で弾けるのだ。はじめは鍋の食材を足していた私達の追加注文は、いつのまにか大量のマンゴーミルクで占められるようになった(辛い舌をミルクが包み込んでくれるまさに慈雨のような飲み物だ)。辛味を増してくる鍋を、そしてそのスープをふんだんに吸った食材との戦いはなかなかに手ごわい。いつしか私達の食卓に会話は無くなり、二人の目はそれぞれの手元の進捗を見つめていた。白菜でラム肉を包み込み食べる私、そしてついにお代わりが叫ばれなくなった豚のから揚げの器を見直し、淡々と肉を平らげるN君。
戦いが終わった時、そこには真っ赤になったスープを湛える鍋と、満腹でもありそして辛さを堪能しすぎた私達が残っていた。サムズアップなのかギブアップなのか分からない腕のあげ方をするN君、そして宙に向けて息を吐き続ける私。なにか良く分からない達成感がそこにはあった。火鍋の器は唐辛子を避けて食べるものだということをレクチャーされ、リベンジに燃えるまで続く達成感が。
※本コラムは事実を盛ったフィクションであり、現実の県民性や奨励会員や店とはあまり関係がありません。
糸谷哲郎